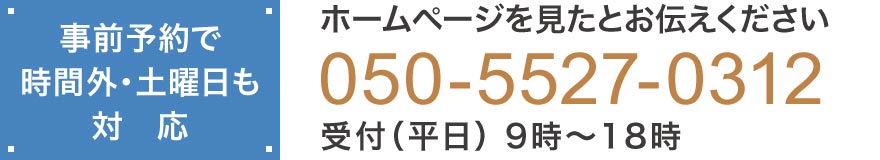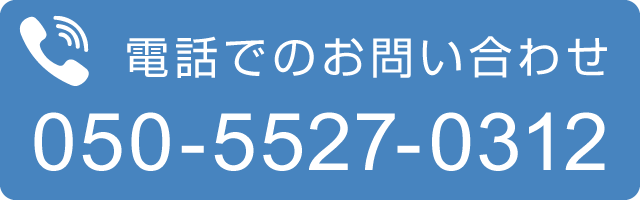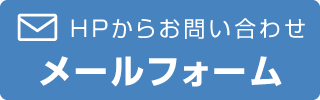Author Archive
明日の経営を考える―名経営者・哲人の金言①
皆さま,こんにちは。
弊所のブログをご覧いただき,ありがとうございます。
1はじめに
弊所の開設前後を通じ,ご縁をいただいた中小企業の皆さま,個人事業主の皆さまの経営を法務・税務等においてサポートさせていただいておりますが,小さいながら自ら事業経営に携わる立場になりました。それ故に以前と比べ,名経営者とされる方々が著した啓発本を読んだり,志を同じくする方々が運営する勉強会に参加したりして,企業経営について考えを巡らせる時間が多くなりました。
現在は,変化が非常に激しい時代です。日々刻々と変化する状況に即応する柔軟性が大切であることはいうまでもありません。しかし,他方で,時代や業種を問わず,企業経営に妥当する普遍的な価値観や理念というものも確実に存在すると思います。私たち企業経営に携わる者は,そのような普遍的な価値観や経営理念をしっかりと確立し,それらを根っこに据えて事業運営に当たるとともに,自社内外にそれらを浸透させる使命を負っている旨の思いを日々強くしているところです。
私は,生ある限り,自らの人生や経営について考える果てなき旅を続けることになります。
そこで,自戒の意味も込めて,これから不定期に名経営者・哲人の金言を紹介させていただき,自らの思考を深め,あるいは,振り返りの機会にしたいと思います。
2「成功は運のせいである。失敗は自分のせいである。」(松下幸之助さん)
~私自身の経営については,このように考えてやってきた。すなわち物事がうまくいった時は〝これは運がよかったのだ〟と考え,うまくいかなかった時は〝その原因は自分にある〟と考えるようにしてきた。つまり,成功は運のせいだが,失敗は自分のせいだということである。
物事がうまくいった時に,それを自分の力でやったのだと考えると,そこにおごりや油断が生じて,次に失敗を招きやすい。実際,成功といっても,それは結果での話であって,その過程には小さな失敗というものがいろいろある。それらは一歩過てば大きな失敗に結びつきかねないものであるが,おごりや油断があると,そういうものが見えなくなってしまう。けれども〝これは運がよかったから成功したのだ〟と考えれば,そうした小さな失敗についても,一つひとつ反省することになってくる。反対に,うまくいかなかった時に,それを運のせいにして,〝運が悪かった〟ということになれば,その失敗の経験が生きてこない。自分のやり方に過ちがあったと考えると,そこにいろいろ反省もできて,同じ過ちはくり返さなくなり,文字通り「失敗は成功の母」ということになってくる。~
【出典:松下幸之助著「実践経営哲学」】
非常に深い内容ですよね。私も全くそうですが,人間は,とかく物事がうまくいっているときは,それを自分の力であると過信し,逆に,物事がうまくいかないとき,あるいは,何かに失敗したときなどは,自らを省みずに,原因を他者に求める,そういう傾向があると思います。しかし,過信等から生じる慢心,驕りこそが,やがて大きな災禍をもたらす原因になりかねません。また,素直な心,謙虚さを大切に,日々反省しこれを活かすことが,その後の成功を引き寄せる着実な一歩になるものと思います。
一見ごく当たり前のことのように思われますが,「言うは易く行うは難し」です。常に肝に銘じ,日々の実践を心掛けたいと思います。
弊所のブログをご覧いただき,改めて感謝申し上げます。皆さまとのご縁に感謝し,日々精進して参ります。

東京・池袋の清水法律会計事務所は、元検察官の代表弁護士・税理士が率いる法律と税務の法律会計事務所です。企業法務から相続、債務整理まで幅広く対応し、特に中小企業の法務支援や事業承継・M&Aでは、他士業との連携によるワンストップ対応が可能です。明確な費用提示と丁寧な対話を重視し、初回相談も安心して受けられる体制を整えています。
お知らせ(令和3年度補正予算-閣議決定)
先日,政府による「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の閣議決定についてお知らせしましたが,令和3年11月26日,本経済対策の財源となる令和3年度補正予算が閣議決定されました。
https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2021/20211125201916.html
政府は,令和3年度補正予算について,「いわゆる『16か月予算』の考え方により,令和4年度当初予算と一体的に編成し,切れ目なく万全の財政政策を実行する。その際,足元のコロナ禍で傷ついた我が国経済を立て直し,自律的な経済成長を実現するために十分な効果を発揮できる規模を確保し,その可能な限り迅速な執行を図るとともに,感染再拡大時にも,必要な対策を躊躇なく機動的に講じることが可能になるよう十分な備えを整える。」としております。
政府には有言実行,すなわち,事業復活支援金等が,それらを必要とする事業者の皆さまに可及的速やかに行き渡り,これらの施策が真に皆さまの事業運営の下支えとなるよう,今般閣議決定された補正予算案の一日も早い国会審議入り・成立が期待されます。
関連情報については,今後随時ご紹介申し上げますが,要件を満たす事業者の皆さまにとっては,貴重な給付金の支給になりますので,皆さまにおいても,今後公表される情報等に十分ご留意ください。

東京・池袋の清水法律会計事務所は、元検察官の代表弁護士・税理士が率いる法律と税務の法律会計事務所です。企業法務から相続、債務整理まで幅広く対応し、特に中小企業の法務支援や事業承継・M&Aでは、他士業との連携によるワンストップ対応が可能です。明確な費用提示と丁寧な対話を重視し、初回相談も安心して受けられる体制を整えています。
お知らせ(コロナ克服・新時代開拓のための経済対策-閣議決定)
政府は,令和3年11月19日,「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を閣議決定しました。(https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html)
本経済対策は,1.新型コロナウイルス感染症の拡大防止,2.ウィズコロナ下での社会経済活動の再開と危機管理の徹底,3.未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動,4.国民の安全・安心の確保,の4つを柱とする総合的な経済対策であり,それぞれ種々の施策が示されています。
1.新型コロナウイルス感染症の拡大防止の中では,「感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活・暮らしの支援」が掲げられ,事業者への支援策として,事業復活支援金の支給(経済産業省所管)や日本政策金融公庫等を通じた資金繰り支援(財務省,経済産業省,金融庁,内閣府,農林水産省所管)などが示されました。
事業復活支援金は,新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者,フリーランスを含む個人事業主に対して,地域,業種を限定しない形で,令和4年3月までの事業継続の見通しを立てられるよう事業規模に応じた給付金を支給するものです。具体的には,事業収入が基準期間同月比で50%以上減少した事業者について,法人は事業規模に応じて上限250万円,個人事業主は上限50万円の範囲内で,基準期間の事業収入からの減少額が給付されます。また,事業収入が基準期間同月比30%~50%売上減少した事業者に対しても,法人は事業規模に応じて上限150万円,個人事業主は上限30万円の範囲内で,基準期間の事業収入からの減少額が給付されます。また,不正防止の措置として,商工団体や士業,金融機関等による事前確認を実施するとともに,事務負担を軽減すべく,電子申請を原則とするなど,可能な限り簡便な手続とするようです。
今後手続等の詳細が決まりましたら,政府から追加公表がなされます。要件を満たす事業者の皆さまにとっては,貴重な給付金の支給になりますので,今後公表される情報等に十分ご留意ください。顧問先の皆さまに対しては,弊所から改めてご案内させていただきます。

東京・池袋の清水法律会計事務所は、元検察官の代表弁護士・税理士が率いる法律と税務の法律会計事務所です。企業法務から相続、債務整理まで幅広く対応し、特に中小企業の法務支援や事業承継・M&Aでは、他士業との連携によるワンストップ対応が可能です。明確な費用提示と丁寧な対話を重視し、初回相談も安心して受けられる体制を整えています。
教えて死後の手続!改葬,永代供養墓の利用,散骨ってどうすればいいの?
皆さま,こんにちは。
弊所のコラムをご覧いただき,ありがとうございます。
大切な家族とのお別れは,いつか必ず経験することになります。
できれば永遠に避けて通りたいと願っても,いつかは必ずお別れの時が訪れます。
大切な人を失った喪失感や悲しみに打ちひしがれながらも,必要な手続を遺漏なく行っていかなければならず,残されたご遺族の方々には相当な負担がかかることになります。
大切な人を失った後の手続として,皆さまが一般的に思い浮かべる事柄としては,葬祭関係の手続と遺産相続に関する手続が挙がられるのではないかと思います。
後者について,弊所は,法務税務の両面において相続に関するご相談やご依頼を常時受け付けておりますので,お困りごと等がございましたら,お気軽にご連絡いただきたく存じますが,一般論を簡潔に申し上げますと,遺言の有無を確定させた上で,遺言があれば,当該遺言を執行する手続を行うことになります。遺言がない,あるいは,遺言はあるものの,当該遺言の内容だけでは,遺産の分配を完結させることができない場合には,相続人の範囲等を確定させた上で,対象者全員による遺産分割協議を進めることになります。これらを経て,納税額が存する場合には,被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納付手続を済ませる必要があります。
この遺産相続に関する手続を進めるだけでも,ご遺族の方々には相当な負担がかかることになりますよね。
本日は,前者の手続,すなわち,葬祭関係の手続について,押さえておいていただきたい基本的な内容を整理しておきたいと思います。
1死後必ず必要になる手続
大切な家族を失った場合,残された家族は,被相続人の死亡を,その本籍地又は住居地の市区町村役場に届け出なければなりません。このことは,「戸籍法」という法律に規定されています。一定の届出義務者が,被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に行わなければならず,原則として医師が作成する死亡診断書又は死体検案書を添付して届出を行うことになります。
届出義務者について,戸籍法第87条は,以下のように規定しています。
「戸籍法第87条 次の者は,その順序に従って,死亡の届出をしなければならない。ただし,順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主,地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は,同居の親族以外の親族,後見人,保佐人,補助人,任意後見人及び任意後見受任者も,これをすることができる。」
同居の親族等に該当する方々は,同居の家族等が亡くなった場合,戸籍法の規定に従って,死亡の届出を行わなければなりません。期間の計算に当たり,初日を算入するかどうかは,対象となる内容によって異なります。この点,戸籍の届出に関しては,戸籍法第43条の規定により,初日を算入する扱いになっています。
同居の親族等であれば,通常,家族等の死亡をその当日のうちに知るのがほとんどであると思われます。たとえば,死亡者をA,届出をすべき同居の親族をBとし,Aが令和3年11月1日に亡くなり,BがAの死亡をその当日に知ったというケースであれば,Aが死亡した11月1日を期間計算において算入することになりますので,同月7日までに届出を行わなければなりません。届出期間の終了日が,日曜祝日等の閉庁日の場合,翌開庁日に受理してもらえますが,記載内容や添付書類の不備を指摘されるなどして,追加の対応が必要になることもあり得ますので,きちんと届出期間を念頭に置いた上で,余裕をもって対応することが大切です。
この死亡の届出に関し,虚偽の届出を行った者に対しては,「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」という刑事罰が科せられます。また,亡くなった家族等に係る死亡について,正当な理由なく期間内にすべき届出をしない者に対しては,「5万円以下の過料」という行政罰が科せられますので,注意が必要です。
家族等が亡くなった場合,通夜,葬儀・告別式を執り行い,故人の遺体を荼毘に付した上で,用意されたお墓に焼骨を納めるのが一般的な流れだと思います。
故人の遺体の埋葬や火葬等に関して規定する法律が,「墓地,埋葬等に関する法律」です。
この法律は,「第一章 総則」「第二章 埋葬,火葬及び改葬」「第三章 墓地,納骨堂及び火葬場」「第四章 罰則」の四章で構成されています。第一章は,法律の目的や各用語の定義規定を設けています。第二章は,私たちが埋葬や火葬を行うに当たって,守るべきルール等を規定しています。第三章は,墓地,納骨堂又は火葬場を経営する者たちが守るべきルール等を規定し,第四章は,この法律の規定に違反した者に対する刑事罰を規定しています。
私たちが家族等を亡くし,火葬等を行うに当たり,留意しなければならない規定は,この法律の第3条~第5条までの規定であり,以下のとおりです。
「第3条 埋葬又は火葬は,他の法令に別段の定があるものを除く外,死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ,これを行ってはならない。但し,妊娠七箇月に満たない死産のときは,この限りでない。
第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は,墓地以外の区域に,これを行ってはならない。
2 火葬は,火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。
第5条 埋葬,火葬又は改葬を行おうとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は,埋葬及び火葬に係るものにあっては死亡若しくは死産の届出を受理し,死亡の報告若しくは死産の通知を受け,又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が,改葬に係るものにあっては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行うものとする。」
故人を葬る方法としては,「墓地,埋葬等に関する法律」を前提にすれば,大別して「埋葬」という方法,すなわち遺体をそのままお墓(土中)に葬る方法と,「火葬」,すなわち遺体を焼き,その焼骨をお墓に埋蔵又は納骨堂に収蔵する方法の2つが想定されます。現在の日本では,ほとんどの場合が後者のパターンであり,「埋葬」の方法が行われることは極めて稀であると思われます。ですから,遺族の方々が,市区町村長から受けるべき許可証は,通常「火葬許可証」になります。
2改葬,永代供養の方法
先祖伝来の立派なお墓があり,檀家になっている菩提寺があれば,当該お墓に故人の焼骨を埋蔵し,当該菩提寺の僧侶にお墓の管理や供養などをお願いすることになります。
しかし,核家族化や都市部への人口集中が進む今日,子の世代が,地方の田舎に老親を残しつつ,東京,大阪等の大都市で生活や仕事をしているようなケースが少なくありません。そういうケースでは,田舎の菩提寺を頼りたくても,日常の行き来が難しく,それが困難であることが少なくないように思います。また,かねて菩提寺の僧侶との折り合いが悪いため,故人が亡くなったのを機に,菩提寺を自分たちの生活拠点に近い別の寺に変更したいと考えるようなケースもあるでしょう。
さらに,皆さまも,「永代供養墓」という言葉をお聞きになったことがあると思います。最近,少子化や核家族化等の進展に伴い,利用が増えている比較的新しいお墓の利用形態です。従来は,家ごとにお墓を建立,維持・管理し,子孫に代々受け継いでいくのが一般的な考え方でしたが,これには当然に相応のお墓の維持管理コスト等がかかります。これに対し,永代供養墓は,霊園や墓地の管理者が遺族に代わって供養・管理をしてくれるお墓ですので,契約に際して永代供養料を支払う必要はありますが,その後の維持管理コストは不要であり,トータルのコストを大分抑えることができるようです。少し寂しい感じもしますが,残される家族にできるだけ負担をかけたくないといった思いから,早くから永代供養墓の利用を検討し,必要な契約手続等を済ませておくケースが徐々に増えているそうです。
故人が生前から永代供養墓の利用に必要な準備等を進めていたケースでは,死亡を届け出た市区町村長から火葬許可証を入手し,故人の遺体を荼毘に付した上で,故人が既に契約締結した永代供養墓に焼骨を埋蔵します。また,故人が生前に契約をしていなかった場合でも,故人の遺志を尊重し,永代供養墓の利用を検討する場合はあり得ます。このような場合も,市区町村長から火葬許可証を入手し,故人の遺体を荼毘に付した上で,遺族が自らの立場で特定の霊園等と永代供養墓の契約を締結し,当該供養墓に焼骨を埋蔵することになるでしょう。
問題は,市区町村長から火葬許可証を入手し,一旦先祖伝来のお墓に焼骨を埋蔵したが,上記のような理由から,菩提寺を従来の寺から自分たちの生活拠点に近い別の寺に変更した上で焼骨を移し替えたい,あるいは,今後の維持管理コストを軽減するため,焼骨を永代供養墓に移し替えたいといった希望がある場合です。これらの場合,どのような手続を踏めばよいのでしょうか?
手続の詳細や費用等は,対象となるお寺等によって異なりますので,その時点で必要になる手続や費用を確認しながら,菩提寺の変更や焼骨の移し替えを行っていただく必要がありますが,ここでは,手続の概要を整理しておきます。
菩提寺の変更に伴う焼骨の移し替えの場合であれ,永代供養墓の利用に伴う焼骨の移し替えの場合であれ,既にお話しした「墓地,埋葬等に関する法律」が規定する特定の手続を踏む必要があります。いずれの場合であっても,同法律が規定する「改葬」の手続が必要になります。「改葬」とは,「埋葬した死体を他の墳墓に移し,又は埋蔵し,若しくは収蔵した焼骨を,他の墳墓又は納骨堂に移すこと」(墓地,埋葬等に関する法律第2条第3項)と定義されています。非常に細かい話で恐縮ですが,同法律では,故人の遺体を火葬した後の焼骨を墳墓に納めることを「埋蔵」として,火葬した後の焼骨を納骨堂に納めることを「収蔵」として,用語を使い分けています。
上記のとおり,改葬を行おうとする者は,市区町村長の許可を受けなければならず(墓地,埋葬等に関する法律第5条第1項),これが改葬許可になります。
菩提寺の変更に伴う焼骨の移し替えの場合も,永代供養墓の利用に伴う焼骨の移し替えの場合も,事前に,現在焼骨を埋蔵するお墓がある市区町村から「改葬許可証」を取得する必要があります。この許可申請は,対象の市区町村に対し,改葬許可申請書を提出して行いますが,添付書類として,焼骨の移転先から入手する「受入証明書」と現在の焼骨管理者から入手する「埋蔵・収蔵証明書」を併せ提出する必要があります。
いずれの場合も,対象の市区町村から改葬許可書を取得した上で,現在焼骨を埋蔵するお墓のある菩提寺において「墓じまい」を行い,その後取り出した焼骨を,変更後の菩提寺が管理するお墓又は永代供養墓に埋蔵することになります。その際,従来の菩提寺から,離壇を思い止まるよう執ように説得されたり,法外な離檀料を請求されたりして,トラブルに発展することもあるようです。
墓じまいをするに当たり,菩提寺の住職に閉魂供養(閉眼供養)を行ってもらった場合,同供養に伴う相応額の御布施は,当然に支払うとして,離壇するか否かは,日本国憲法が保障する信教の自由(憲法第20条)に基づき,各人が何人からも干渉等を受けずにそれぞれ自由に決めることができる事柄です。寺院も,取り巻く経営環境が徐々に厳しくなるなか,檀家からの御布施等は貴重な収入源ですので,離壇を思い止まらせたい胸の内は理解できます。しかし,檀家が離壇しようとするのを不当に阻止するようなことは許されません。
また,法外な離壇料の請求についても,当事者双方の契約において,お互い納得して当該金額の離壇料に関する取決めを交わしていたような場合はともかく,そのようなケースは極めて稀でしょう。契約上の取決め等がないにもかかわらず,従来の菩提寺から法外な離壇料を請求されても,これは明らかに根拠を欠くものですので,支払要求に応じる必要はありません。
仮に,離壇に当たり,このようなトラブルに巻き込まれ,ご自分の力だけではうまく解決が付かない場合には,早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
3散骨の方法
散骨とは,故人の遺骨をパウダー状になるまで粉砕し,海や山などの自然に葬る方法です。
地球規模で見れば,世界各地に見られる比較的ポピュラーな葬送法のようですが,日本では,散骨の習慣はなく,現在の我が国には,散骨に関して規定する法律は存在しません。
専門の粉骨業者に依頼するなどして,遺骨を一片2mm以下のパウダー状になるまで粉砕することが前提ですが,遺骨を粉々に粉砕した上で,明らかに他者に迷惑を及ぼすおそれのない場所で行う散骨については,我が国の法律に抵触することはありません。
ただ,散骨を規制する法律はなくても,各地の自治体が条例で散骨を独自に規制しているケースはあります。散骨を検討する場合には,検討する候補地での散骨が当地の条例によって規制されていないかどうか,事前に調査し,必要な手続があれば,決められた手続をきちんと踏むことが大切です。
散骨には,一般に,海洋散骨,山間散骨があり,いずれの場合でも,遺族自らが散骨を行う方法のほか,専門の散骨業者に散骨を委託する方法などがあります。
荼毘に付した後の焼骨を自宅等で保管中であれば,上記のとおり遺骨をパウダー状になるまで粉砕するなどして,比較的スムーズに散骨を行うことができると思われます。他方,焼骨を既に菩提寺が管理するお墓に埋蔵しているケースであれば,「2改葬,永代供養の方法」の該当箇所で言及したとおり,従来の菩提寺から,離壇を思い止まるよう執ように説得されたり,法外な離檀料を請求されたりして,トラブルに発展することもあるようです。
根拠を欠く法外な離壇料の支払要求に応じる必要など全くありませんが,仮に,このようなトラブルに巻き込まれ,ご自分の力だけでは解決が図れそうにない場合には,早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
なお,散骨を行うために,菩提寺等に対し,焼骨の引き渡しを求めた場合に,相手先によっては,市区町村が発行する改葬許可証の提示を頑なに求めてくるケースもあるようです。「墓地,埋葬等に関する法律」が規定する「改葬」の定義,すなわち,「埋葬した死体を他の墳墓に移し,又は埋蔵し,収蔵した焼骨を,他の墳墓又は納骨堂に移す」という改葬の定義を前提にすれば,散骨が,同法律の規定する「改葬」に当たらないことは明らかですので,改葬許可証の提示は不要と考えるのが自然であると思われます。
弊所のコラムをご覧いただき,改めて感謝申し上げます。皆さまとのご縁に感謝し,日々精進して参ります。

東京・池袋の清水法律会計事務所は、元検察官の代表弁護士・税理士が率いる法律と税務の法律会計事務所です。企業法務から相続、債務整理まで幅広く対応し、特に中小企業の法務支援や事業承継・M&Aでは、他士業との連携によるワンストップ対応が可能です。明確な費用提示と丁寧な対話を重視し、初回相談も安心して受けられる体制を整えています。
サウナで浮かぶマジックセンテンス!!
皆さま,こんにちは。
弊所のブログをご覧いただき,ありがとうございます。
今日は,私の大好きなサウナをネタに思うところを気ままに綴りたいと思います。
1サウナの効用
コロナ禍が想定以上に長引き,行動自粛が求められる中,私も,基本的にサウナの利用を控えていましたが,9月末日をもって緊急事態宣言が解除されたことから,感染症対策をきちんと講じた上で,少しずつサウナ通いを再開しました。
サウナは,全身の血行が良くなり,利用後言葉では表現し難い爽快感・幸福感が得られます。私にとって,サウナは健康の維持増進にとって欠かせないものです。
サウナの効用については,様々な内容が語られていますが,私も愛読している「人生を変えるサウナ術 なぜ,一流の経営者はサウナに行くのか?」(KADOKAWA 本田直之・松尾大著)によれば,物心の両面及び社会的効用として,それぞれ以下のような効用があるとされています。
<フィジカル的効用>
①運動後の爽快感,リフレッシュ効果
②良質な睡眠が得られる
③ご飯が驚くほど美味しくなる
④免疫力が高まり,風邪を引きにくくなる
⑤心臓病,アルツハイマー病などの健康リスク低減
<メンタル的効用>
①自律神経が鍛えられ,精神が安定する
②幸福を感じやすくなる
③デジタルデトックスとマインドフルネス
<ソーシャル的効用>
①心と身体の距離がゼロになる
②サードプレイスとしてのサウナ
③サウナでつながるコミュニティの輪
これらの効用については,サウナを愛する私の実体験を通じても,どれも積極的効用として頷けるものです。ですので,個人差等は当然あり得ますが,サウナの利用により,これらの効用が得られることについては,間違いないと太鼓判を押します。
各効用の詳しい内容について,興味のある方は,是非上記の本を読んでみてください。ちなみに,メンタル的効用の③とは,どういうことか少し触れておきます。現在私たちの身の回りにはスマホやタブレット等のデジタル機器が溢れ,ともすれば大量の情報に振り回されつつあります。サウナは,基本これらデジタル機器の持ち込みが禁止されていますので,サウナの利用により,デジタル機器の利用,ひいては溢れる情報から半ば強制的に遮断される状況が作出されます。この点を捉えて,「デジタルデトックス」と表現されています。そして,サウナがストレスフルな外界の情報をシャットダウンして利用者をしてリラックスさせ,頭をクリアにして自身の内面を向き合わせる,究極のマインドフルネスが実現されるというのです。
サウナの利用を通じて思うことは,本当に良いことづくめであり,マイナスの点が思い浮かびません。興味のある方には,是非試していただきたいと思います。
ただ,ご留意いただきたいのは,心臓疾患を既に抱えていらっしゃる方や,動脈瘤や静脈瘤など血管にコブが既にできている方などです。上記のとおり,サウナには心臓疾患の予防効果が期待されるのですが,既に心臓疾患等を患っていらっしゃる方は,サウナの利用に当たり,必ず医師に相談の上利用するようにしていただきたいと思います。
2温冷交代浴で「ととのう~」
サウナの利用により,上記のとおり,様々な積極的効用が得られるのですが,サウナ室に入って汗を流すだけではダメです。いわゆる温冷交代浴という「サウナ→水風呂→外気浴」というサイクルを,お好みで何セットか繰り返す利用法が推奨されています。この温冷交代浴により,「ととのう」という極上の感覚が得られ,多くの利用者をサウナの虜にするのです。
「サウナ→水風呂→外気浴」というサイクルの中で,私たちの身体にどのような変化が起きているかについて,上記の本で分かりやすく解説されていますので,該当部分を引用させていただきます。
~ サウナ室に入ると,身体は熱い空気に包まれてじわじわと汗が出てくる(汗が出るまでの時間には個人差があるが,サウナに入って汗を書くのに慣れれば慣れるほど発汗までの時間は短くなり,サウナ室内に足を踏み入れるとほとんど同時に,クリスタルのようなきめ細かい汗が全身の毛穴から噴き出してくる)。体内の老廃物が汗とともに排出され,身体の物質交換が進んで疲労回復に繋がる。
そうしてしばらくサウナにいると,だんだん熱くなってきて,40℃近くまで上昇した体温を冷まそうと皮膚の表面の血流量が増加し,脈拍も平常時の2倍ほどの速さになる。
「サウナ=気持ちいい」というわけではなく,むしろ不快感が増して交感神経が活発になる。80~90℃もあるサウナ室に何時間も居たら死んでしまうので,身体が危険信号を出すために交感神経が活発になるのは生物としては当たり前のことだ。
そうして「熱くなってきたな・・・・・・」となってきたところで,サウナ室を出て水風呂に入る。温められていた身体が冷たい水で急速に冷やされ「気持ちいい~!」となるところなので,サウナ―の中にも特に水風呂をメインの楽しみにしている人は多い。
しかしながら,水風呂でも,リラックスしているときに優位になる副交感神経ではなく,交感神経が優位になる。16℃などの水風呂(場所によっては一桁台の温度の水風呂もある)にずっと浸かっていたら,体温はどんどん下がり,またもや生命の危険に晒されることになるからだ。
水風呂も十分に浸かったところで,浴槽を出て,外気浴スペースで休憩を行う。このとき,サウナ→水風呂で大きく交感神経優位になっていたところから,反発して逆に副交感神経が優位となり,身体全体が一気にリラックスモードに入る。水風呂によってぎゅっと収縮していた血管が解放され,体表温度も脈拍も平常時近くに戻る。
この交感神経優位から副交感神経優位に自律神経がスイッチする際の感覚,極端に暑かったり寒かったりした環境から,平常の環境に戻ってくると「ホッとする」。
この,自分の基準である体温や脈拍へと一旦リセットされ,リブート(再起動)されるときの,いうなれば野性的な感覚が,サウナにおける爽快感であり,「ととのう」という感覚の正体だ。~(「人生を変えるサウナ術 なぜ,一流の経営者はサウナに行くのか?」(KADOKAWA 本田直之・松尾大著)P32~34より引用)
サイクルを構成する,サウナ,水風呂,外気浴は,「ととのい」を得るためには,どれも欠かすことのできない必須の要素です。熱さと寒さという両極の極限状態に連続して身を置くことで,自律神経のうちの交感神経が優位になります。そして,水風呂から出て椅子やリクライニングシートに身を委ねて休憩を取ることで,一転して副交感神経が優位になり,言葉では表現し難い爽快感・幸福感が得られるのです。例えるなら,身体の中の全細胞が瞬時に生まれ変わり活性化しているような,最高の快感です。
3サウナ室での呟き
「ととのい」を得るために,サウナも水風呂も欠かせないプロセスですが,人によって,どちらに重きを置くか,楽しみにしているかは結構別れるのではないかと思います。私は,長らく水泳をしていたことが影響してか,断然水風呂派であり,サウナ後の水風呂入浴で体感できる「天女の羽衣」に包まれるような極上の感覚がサウナ利用時の大きな楽しみです。利用施設ごとに水風呂の水温はまちまちですが,おおむね16℃前後に設定している施設が多いと思います。私の場合,サウナに8~10分程度入った後,水温16℃前後の水風呂であれば,2~2分30秒程度水風呂に入り,それから10分前後休憩して「ととのい」を得るようなサイクルになります。
最近でこそ,サウナ室内での温熱やそれに伴う発汗も快く感じられるようになりましたが,それでも,入室後の時間経過と共に息苦しさが募っていきます。水風呂というメインディッシュを堪能する上で避けて通れないプロセスではあるものの,通常ではあり得ない85~100℃程度の極限状態に一定の時間身を置くことになるので,時間の経過と共に苦行の様相を呈してきます。
そんなサウナ室での孤独の格闘の中で,私の頭に浮かび,心の内でブツブツと唱える内容があります。江戸幕府の開祖である徳川家康が遺した「東照公御遺訓」であり,宮澤賢治が遺した「雨ニモマケズ」です。いつの時代にも通じる普遍的で,とても貴重な内容ですので,以下,引用させていただきます。
<東照公御遺訓>
人の一生は重荷を負て 遠き道をゆくが如し いそぐべからず 不自由を常とおもえば不足なし こころに望おこらば困窮したる時を思ひ出すべし 堪忍は無事長久の基 いかりは敵とおもへ 勝事ばかり知てまくる事をしらざれば害其身にいたる おのれを責て人をせむるな 及ばざるは過ぎたるよりまされり
<雨にも負けず(現代語訳)>
雨にも負けず
風にも負けず
雪にも夏の暑さにも負けぬ
丈夫な体を持ち
欲は無く
決して怒らず
いつも静かに笑っている
一日に玄米四合と
味噌と少しの野菜を食べ
あらゆることを自分を勘定に入れずに
よく見聞きしわかり
そして忘れず
野原の松の林の陰の
小さな萱ぶきの小屋にいて
東に病気の子どもあれば
行って看病してやり
西に疲れた母あれば
行ってその稲の束を負い
南に死にそうな人あれば
行って怖がらなくてもいいと言い
北に喧嘩や訴訟があれば
つまらないからやめろと言い
日照りの時は涙を流し
寒さの夏はおろおろ歩き
みんなにでくのぼーと呼ばれ
褒められもせず
苦にもされず
そういうものに
私は なりたい
改めて各引用文を読んでいますが,いずれも本当に名文ですよね。実り多き人生を歩むうえでの心構え等が凝縮されていますよね。願わくは,「東照公御遺訓」にあるような境地に到達したい,「雨ニモマケズ」で描写されている人物のようになりたいとの思いが,そうさせるのか,サウナ室に入って5分程度が経過し,息苦しさが相当募ってくる頃合いから,これらが頭に浮かび始めます。そして,それぞれ2~3回繰り返し心の中で唱えてからサウナ室を出るのがサウナ利用時のルーティーンになりつつあります。いくら素晴らしい内容であっても,声に出してブツブツやってしまっては,他のサウナーに迷惑ですし,度が過ぎれば,それこそ出入り禁止にもなりかねません。あくまで心の中で,無言で唱えておりますので,ご安心ください(笑)。
このようにサウナは,私にとって,最高のリフレッシュ法であるとともに,貴重な精神修養の場ともなりつつあります(笑)。十分な感染症対策を講じた上,サウナライフを楽しんでいきたいと思います。
本日は,弊所のブログをご覧いただき,改めて感謝申し上げます。皆さまとのご縁に感謝し,日々精進して参ります。

東京・池袋の清水法律会計事務所は、元検察官の代表弁護士・税理士が率いる法律と税務の法律会計事務所です。企業法務から相続、債務整理まで幅広く対応し、特に中小企業の法務支援や事業承継・M&Aでは、他士業との連携によるワンストップ対応が可能です。明確な費用提示と丁寧な対話を重視し、初回相談も安心して受けられる体制を整えています。
忍び寄る無差別殺傷事件の恐怖!「防犯意識を高めよう」
皆さま,こんにちは。
弊所のコラムをご覧いただき,ありがとうございます。
1続発する無差別殺傷事件
本年10月31日の夜,凄惨な事件が発生しました。東京都調布市内を走行中の京王線の電車内において,服部恭太容疑者が居合わせた乗客の会社員男性の胸部を刃物で刺した上,車内にオイルを撒いて放火し,男女16人が重軽傷を負った事件です。不特定多数人が利用する公共交通機関内での無差別殺傷事件であり,被害者の方々やその場に居合わせた方々はもとより,報道等を通じて事件を知った多くの人々を不安と恐怖に陥れる悪質な犯行であり,強い憤りを禁じ得ません。
服部容疑者は,逮捕後の取調べに対し,「小田急線の事件を参考にした。」と供述しているようですが,本年8月6日には,東京都世田谷区内を走行中の小田急線の電車内で,容疑者の男が乗客10人を刃物で切り付けるなどして重軽傷を負わせる殺傷事件が発生しました。今回の京王線無差別殺傷事件は,服部容疑者が,小田急線事件を模倣して実行したとみて間違いないでしょう。不特定多数人を狙った無差別事件は,いわゆる模倣犯と位置付けられ,同種の第2・第3の犯行を誘発する危険性が指摘されています。
電車内で乗客が刃物などで襲われる事件は,過去にも起きています。1995年3月発生のいわゆる地下鉄サリン事件では,地下鉄日比谷線など3路線の電車内に猛毒のサリンが撒かれ,13人が死亡,600人超が負傷する大惨事となりました。また,2015年6月には,神奈川県内を走行中の東海道新幹線内で男が焼身自殺を図り,巻き添えになった女性1人が死亡し,20人以上が重軽傷を負いました。さらに,2018年6月にも,神奈川県内を走行中の同新幹線内でナタを持った男が乗客に切り付け,男性1人が死亡,女性2人が負傷しました。
長引くコロナ禍の影響により,将来不安を募らせる人々は少なくありません。人間関係や仕事に行き詰り,将来を悲観して,今回の小田急線事件,京王線事件等を模倣した同種犯行がこれ以上繰り返されないことを切に祈るばかりです。
2無差別殺傷事件は極めて重罪
小田急線事件及び京王線事件については,現在,捜査当局が各事件の真相解明に向けて鋭意捜査中であり,動機等の解明が待たれるところですが,報道ベースで明らかにされている事実関係を前提に,各事件ではどのような犯罪の成否が問題となり,どの程度の重さの刑事責任が科され得るのかについて,若干整理しておきます。
まず,刃物を電車内に持ち込み携帯していた行為については,銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪が成立します。また,その刃物を使って,電車内に居合わせた乗客を刺したり,切り付けたりして負傷させれば,殺意の有無に応じて,刑法204条の傷害罪や同法199条,203条の殺人未遂罪の成立が問題になります。幸いにも,両事件で命を落とされた方はいらっしゃいませんでしたが,2015年及び2018年の各事件のように,刃物で襲われた方が命を落とされる事態になれば,殺人既遂罪の成立が問題になります。法律には,犯罪と科せられる刑が明確に定められる建前(これを「罪刑法定主義」といいます。)となっております。傷害罪については,刑法204条により「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑が定められ,殺人罪については,同法199条により「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という刑が定められています。なお,現時点での報道情報を前提にすれば,小田急線事件及び京王線事件では,殺人既遂罪ではなく,殺人未遂罪の成否が問題になりますが,既遂・未遂のいずれであっても,法律が定める刑,つまり法定刑は,上記のとおり,「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という内容に変わりはなく,未遂罪の場合には,刑法43条により,刑の減軽操作が行われる余地がある点で違いがあります。
さらに,両事件の犯人は,サラダ油やオイルを撒いて,各車内で放火行為にも及んでいます。車内の燃えの詳細な情報等を待たずして,各犯人に成立する罪を特定してお話しすることはできませんが,報道ベースの情報を前提にすれば,いずれの犯行においても,刑法108条が定める現住建造物等放火罪の成否が問題となり得ます。同罪も刑法犯の中では重罪として位置付けられ,同条により「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という刑が定められています。
このように,両事件で行われた犯行内容を前提にすれば,各犯人に対しては,相当重い刑事責任が科せられることになります。刑事罰には,当該犯罪を抑止する効果も期待されており,今回のような卑劣な無差別殺傷事件が短期間のうちに繰り返される事態になれば,罰則強化の議論が行われても不思議ではなく,現実に発生した事象を踏まえ,罰則強化を含む必要な議論が活発に展開されることはむしろ歓迎すべきだと思います。ただ,京王線事件の服部容疑者が供述するように,自己の将来を悲観し,自暴自棄の末に死刑に処せられることを望んで無差別殺傷の犯行に及ぼうとする者に対しては,対象犯罪の厳罰化による犯罪抑止効果が期待できないことに留意すべきでしょう。
3無差別殺傷事件に対する対応
上記のとおり,電車内での凄惨な事件は,過去にも繰り返されており,その都度,鉄道各社は,国土交通省や警察当局等と連携しながら,各種対策を講じてきました。具体的には,警察官や警備員の見回り強化や,駅施設構内及び電車内の防犯カメラの設置などです。鉄道各社に対しては,これら既存の対策の強化徹底が求められますが,各社は,これら事件の発生を受け,不審者に対する声掛けや所持品検査の強化,不審者情報の割出し等へのAI技術の活用などを検討しているそうです。凄惨な事件を未然に防止する上で有効な対応策の一日も早い充実強化が期待されます。
そして,行政や鉄道各社の対応策の充実強化に増して重要なのが,私は,電車等の公共交通機関を利用する私たち一人ひとりが防犯意識を高めることだと思います。私たちが,現実に発生してしまった小田急線事件及び京王線事件等を,当事者意識をもって真剣に受け止め,「公共交通機関は安全ではない」旨を自覚し,駅施設構内や電車内において警戒心を解かず,仮に不審物や不審人物に気付いたら,躊躇せずに各社従業員や警備員,警察官への通報等を徹底するなどの対応が,続発する無差別殺傷事件から私たちの身の安全を守る上で,殊のほか重要であり,有効に機能し得るものと思えてなりません。
弊所のコラムをご覧いただき,改めて感謝申し上げます。皆さまとのご縁に感謝し,日々精進して参ります。

東京・池袋の清水法律会計事務所は、元検察官の代表弁護士・税理士が率いる法律と税務の法律会計事務所です。企業法務から相続、債務整理まで幅広く対応し、特に中小企業の法務支援や事業承継・M&Aでは、他士業との連携によるワンストップ対応が可能です。明確な費用提示と丁寧な対話を重視し、初回相談も安心して受けられる体制を整えています。
お知らせ(全館停電に伴う相談対応等休止【11月13日(土)】)
弊所は,年末年始及び土日祝日を除く,平日の9時~18時を営業時間としつつ,事前予約をいただくことで,平日18時以降及び土曜日については,相談等の対応をさせていただいております。
しかし,令和3年11月13日(土)については,弊所が入館するダイヤゲートにおいて,電源設備年次法定点検に伴う全館停電が予定されております。
つきましては,ご迷惑をお掛けし誠に恐縮ですが,同日につきましては,終日事前予約による相談対応等を休止させていただきます。何卒ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

東京・池袋の清水法律会計事務所は、元検察官の代表弁護士・税理士が率いる法律と税務の法律会計事務所です。企業法務から相続、債務整理まで幅広く対応し、特に中小企業の法務支援や事業承継・M&Aでは、他士業との連携によるワンストップ対応が可能です。明確な費用提示と丁寧な対話を重視し、初回相談も安心して受けられる体制を整えています。